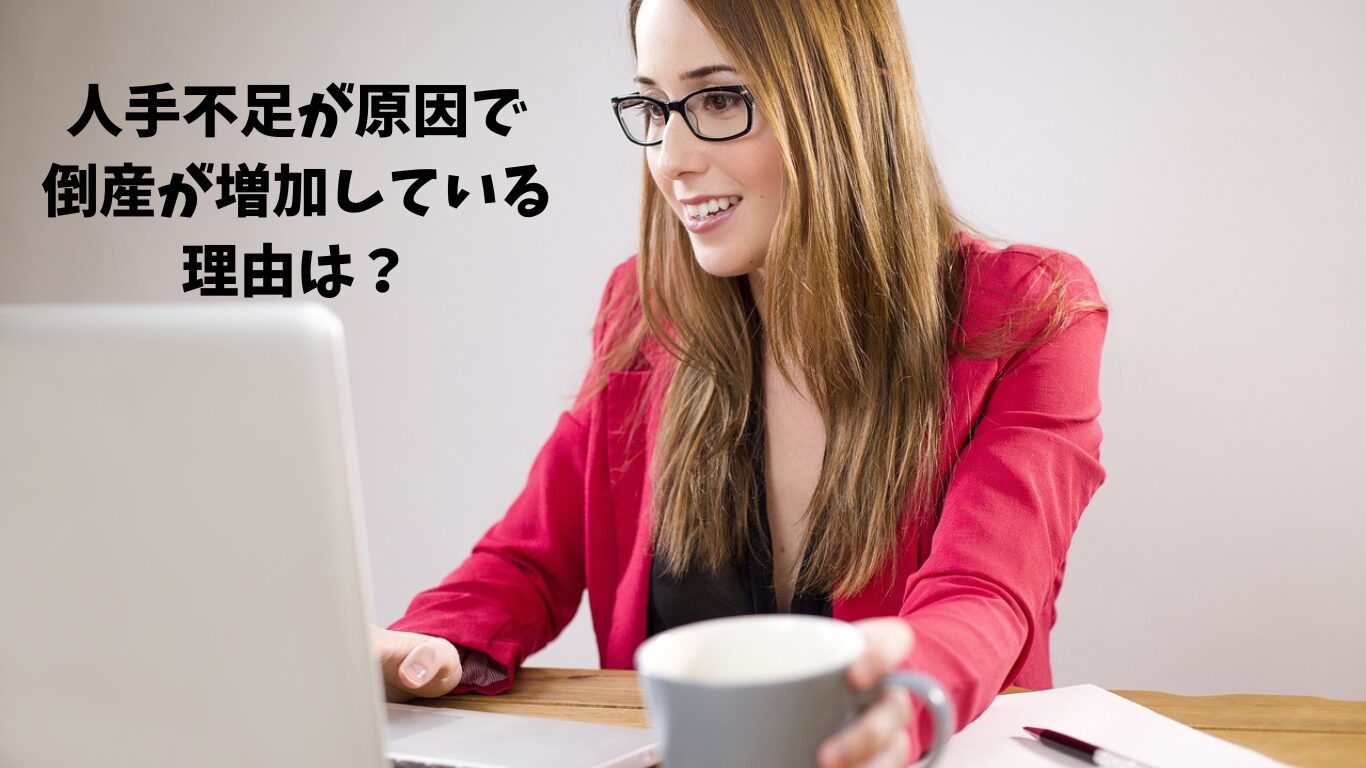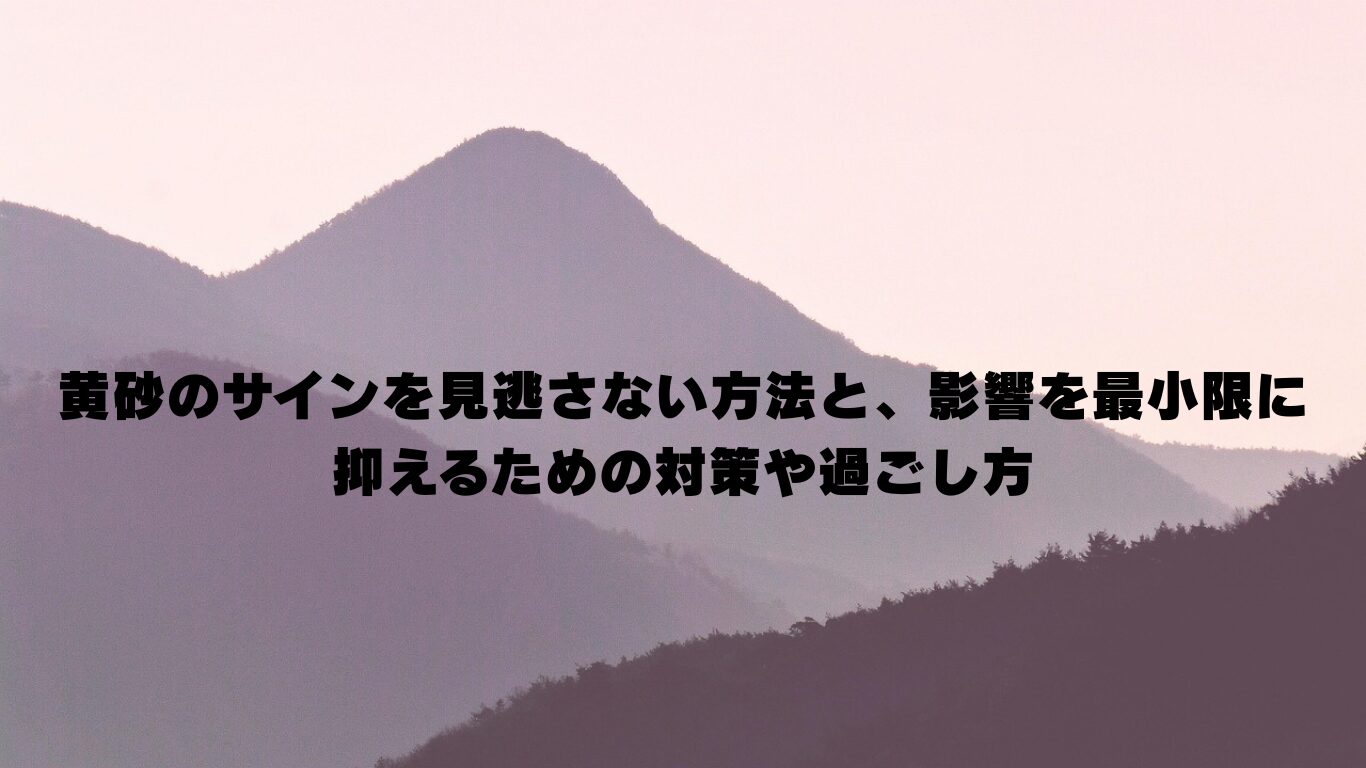近年、日本では人手不足が深刻な社会問題となっています。
特に中小企業では、必要な人材を確保できずに業務が回らなくなり、最悪の場合、倒産に追い込まれるケースも増えています。
帝国データバンクの調査によると、「人手不足」を原因とする企業倒産は年々増加傾向にあり、この問題を放置すればさらなる経済的ダメージが予想されます。
では、なぜここまで人手不足が深刻化しているのでしょうか?
また、影響を受けやすい業種にはどのような特徴があるのでしょうか?
本記事では、人手不足が原因で倒産が増加している理由や、特に厳しい業種について詳しく解説します。
さらに、企業がとるべき対策についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
人手不足が引き起こす倒産の現状
企業にとって「人手不足」は単なる経営課題ではなく、存続そのものを左右する深刻な問題です。
実際に、人材確保ができずに業務継続が困難になり、倒産に追い込まれるケースが増えています。
ここでは、人手不足による倒産の実態や、その主な原因について詳しく見ていきましょう。
人手不足による企業倒産の増加データ
近年、人手不足が原因で倒産する企業が増加傾向にあります。
帝国データバンクの調査によると、2023年の「人手不足倒産」は過去最高を記録しました。
特に、中小企業では十分な労働力を確保できず、事業の継続が困難になるケースが多発しています。
また、業界別に見ると、建設業、介護業、飲食業などで倒産件数が増加しており、これらの業種は慢性的な人材不足に苦しんでいることがわかります。
倒産に至る主な原因とは?
企業が人手不足で倒産に至る主な原因には、以下のようなものがあります。
- 求人を出しても応募が集まらない → 労働人口の減少により、人材確保が難しくなっている。
- 既存社員の負担増による離職 → 人手不足の影響で業務負担が増加し、社員が次々と辞めてしまう。
- 受注はあるのに仕事を回せない → 事業拡大のチャンスがあっても,従業員不足で対応できず、
経営が悪化する。 - 過重労働による生産性低下 → 残った社員が疲弊し、業務効率が落ちることで企業の競争力が低下する。
人手不足の影響を受けやすい業種
人手不足による倒産は特定の業種で特に顕著に見られます。
以下の業種では、人材確保が難しく、倒産リスクが高い傾向にあります。
- 建設業:高齢化が進み、若手の確保が困難。技能を持つ職人の減少が深刻化している。
- 介護・福祉業界:労働条件が厳しく、低賃金のため人材が定着しにくい。
- 飲食業:長時間労働や低賃金の影響で、働き手が集まりにくい。
- 運輸・物流業:ドライバー不足が深刻で、物流の停滞が経済全体に影響を及ぼしている。
このように、人手不足による倒産は特定の業界で顕著に現れています。
なぜ人手不足が深刻化しているのか?
人手不足が多くの企業に深刻な影響を与えているのは明らかですが、そもそもなぜここまで労働力が不足しているのかを理解することが重要です。
ここでは、人手不足が進行する主な要因を見ていきます。
少子高齢化による労働人口の減少
日本では、少子高齢化が進行し、労働市場における若年層の割合が減少しています。
総務省のデータによると、生産年齢人口(15〜64歳)は1995年の約8,700万人から、2023年には7,400万人以下に減少しています。
特に地方では、若者が都市部へ流出することで人手不足が加速しており、地元企業の存続が難しくなっています。
このように、働き手そのものが減少していることが、企業の人手不足を招く大きな要因となっています。
労働環境の問題と人材流出
多くの業界で、長時間労働や低賃金といった労働環境の問題が指摘されています。
特に介護業界や建設業界、飲食業界では、以下のような理由で人材が定着しにくい状況が続いています。
- 低賃金・過酷な労働環境:給料が低く、労働時間が長いため、他の業界へ転職する人が多い。
- キャリアアップの機会が少ない:専門職でない限り、昇給やキャリアの見通しが立ちにくい。
- 休みが取りにくい:特に飲食業や介護業では、休日が少なくワークライフバランスが取りにくい。
このような労働環境の課題が、企業の人材確保を難しくし、結果として人手不足を加速させています。
求職者の仕事に対する意識の変化
近年、働き方に対する意識が変化し、求職者が仕事を選ぶ基準が変わってきています。
特に、以下のような傾向が見られます。
- 安定よりも自由を求める:フリーランスやリモートワークを希望する人が増加。
- ワークライフバランスを重視:長時間労働を避け、柔軟な働き方を求める人が増えている。
- 企業の価値観や社会的責任を重視:SDGsや環境問題に取り組む企業への関心が高まっている。
これにより、従来の「とにかく働く」スタイルの企業では人材を確保しにくくなっているのが現状です。
企業側も時代の変化に対応し、新しい働き方を模索することが求められています。
人手不足が深刻な業種とは?
人手不足は業界全体の問題ですが、特に影響が大きい業種があります。
ここでは、深刻な人材不足に直面している3つの業界について、その背景や課題を詳しく解説します。
介護・福祉業界の人手不足とその背景

介護・福祉業界は、特に深刻な人手不足に陥っています。
厚生労働省のデータによると、2025年には約30万人の介護職員が不足すると推計されています。
主な原因
- 高齢化の進行:高齢者が増え続ける一方で、介護を担う人材が不足。
- 過酷な労働環境:長時間労働・低賃金・肉体的負担が大きい。
- 離職率の高さ:介護職員の3年以内の離職率は約30%と高い。
この業界の人手不足が続けば、十分な介護サービスが提供できず、高齢者やその家族への影響がさらに拡大する可能性があります。
飲食・サービス業界の厳しい現状

飲食業や宿泊業などのサービス業界でも、人手不足が大きな問題となっています。
特に、新型コロナウイルスの影響で一度離職した人材が戻らず、業界全体の労働力確保が難しくなっています。
主な原因
- 低賃金と長時間労働:時給制が多く、不安定な雇用形態が敬遠される。
- 休日が取りにくい:土日や祝日も営業するため、プライベートとの両立が難しい。
- 人手不足による業務負担の増加:少ない人数で回すため、従業員の負担が増大。
これにより、特に個人経営の飲食店などでは閉店を余儀なくされるケースも増えています。
建設業・運輸業も危機的状況に

建設業や運輸業も、人材確保が極めて難しい業界の一つです。
国土交通省によると、建設業の就業者の約35%が55歳以上であり、若手の担い手不足が深刻化しています。
主な原因
- 高齢化による労働者の減少:ベテラン職人が引退する一方で、若手が育たない。
- 肉体労働の厳しさ:体力的な負担が大きく、長期間続けるのが難しい。
- 労働時間の長さ:建設業や運輸業は長時間労働になりやすい。
これらの業界では、労働環境の改善や技術革新(AI・ロボットの導入など)が求められています。
企業がとるべき対策と今後の展望
人手不足は一朝一夕で解決できる問題ではありません。
しかし、企業が適切な対策を講じることで、人材の確保や定着率の向上につなげることが可能です。
ここでは、企業が実践できる具体的な対策を紹介します。
労働環境の改善と働き方改革
従業員が長く働き続けられる環境を整えることは、人材確保の基本です。
以下のような取り組みが求められます。
- 給与・待遇の見直し:競争力のある給与体系を導入し、昇給の機会を増やす。
- 労働時間の短縮:シフト制の見直しや業務効率化を進め、長時間労働を減らす。
- 福利厚生の充実:育児支援や健康管理制度を整備し、従業員の満足度を向上させる。
働きやすい環境を整えることで、離職率の低下や求職者の応募増加につながります。
外国人労働者の活用とその課題
日本では、外国人労働者の受け入れを拡大する動きが進んでいます。
特に、人手不足が深刻な介護・建設・飲食業界では、技能実習生や特定技能制度を活用して人材を確保する企業が増えています。
外国人労働者を活用するメリット
- 即戦力となる人材の確保:特定技能を持つ外国人を採用することで、人材不足を補える。
- 多様な価値観の導入:グローバルな視点を持つことで、企業の発展につながる。
しかし、言語の壁や文化の違い、労働環境の整備といった課題もあり、適切な対応が求められます。
テクノロジーを活用した業務効率化

テクノロジーの導入によって、少ない人員でも業務を効率的に回すことが可能になります。
特に、以下のような技術が注目されています。
- AI・RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)導入 → 単純作業を自動化し人手を減らす。
- 無人店舗・セルフレジの活用 → 飲食・小売業界での省人化が進む。
- オンライン対応の拡充 → テレワークやリモート接客で業務を効率化。
最新技術を活用することで、人材不足の解決だけでなく、企業の競争力向上にもつながります。
企業が労働環境の改善・外国人労働者の活用・テクノロジーの導入といった対策を講じることで、人手不足問題に対処することが可能です。
まとめ
最後までこの記事を読んでいただきありがとうございます。
日本では人手不足が深刻な社会問題となり、特に介護・飲食・建設・運輸業界では倒産のリスクが高まっています。
その背景には、少子高齢化の進行、労働環境の問題、求職者の意識の変化などがあり、今後さらに厳しくなることが予想されます。
しかし、企業が適切な対策を講じることで、人手不足の影響を軽減することは可能です。
具体的には、労働環境の改善、外国人労働者の活用、テクノロジーを導入した業務効率化といった取り組みが重要になります。
この問題を解決するためには、企業だけでなく、政府や社会全体での取り組みが不可欠です。
今後も変化に適応しながら、持続可能な働き方を模索していくことが求められます。